2025年01月17日
阪神淡路大震災30年
昨年元日の能登半島地震の被災者。
もう、心も折れて立ち上がる気力も失せる状況。
ボランティアの人がかけてくれた言葉で前を向けたという。
「大丈夫ですよ。私たちが前を歩いています」
阪神淡路大震災での被災経験者のボランティアだった。
読んだとたんに、記している今さえ、涙がこぼれる。
あの地震で被災した人々が、その後の被災地に
一番に駆け付けたことをいくつも聞いているからだ。
あれほどの地震、あれほどの災害、その後の時間が
ようやく進みかけた9年後。
中越地震が発生した時に、真っ先に助けに入る。
1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)以来、
当時観測史上2回目の最大震度7を記録した地震だった。
鳥取県西部地震でも熊本地震でも東日本大震災でも。
彼らはどこへも駆けつける。
その思いに触れて、押さえようもなく熱いものがこみ上げてくる。
そして、彼らがあの日から、震災に合わないようにと
呼びかけてきてくれていること、進んだ防災減災のための制度に
深く感謝し続ける。
あの日、震災被害にあった地域のラジオが細やかな情報を
流し続け、いかに市民の役に立ったかを評価し、
全国にコミュニティラジオ局が続々と開局された。
今も、コミュニティラジオ局は防災ラジオと称されるゆえんでもあろう。
東海地震に備え、防災情報の収集をし、
また仕事で被災者からの話を聞く機会を多く得、
学んでゆくうちに、いかに阪神淡路大震災がわたしたちに
多くの防災の知恵を授けてくれたか、その事実に胸が苦しくなってくる。
発生の様子。倒壊で命を失わないために。
あるいは、逃げ遅れないために。
今も、たくさんの家屋内外への知恵が教示されている。
あの日。救命措置で一人でも多く救うために、
どれほどの思いで、運び込まれる人々の
処置の順序や、ときに措置の打ち切りをしたか。
あの時。目の前の炎を前に、人々の助けを懇願する様子の前に、
車も入れず、水も出ず、なすすべのない思いを味わったか。
被災者救助に当たった医療関係者や消防隊は、
無念さや無力感から、いつまでも心の傷をおった。
その後、トリアージの制度やD-Matなどが
次々整備され、特殊救助隊や特殊車両の導入となる。
倒壊家屋から助け出された人々の、その後の突然死の関連から
クラッシュ症候群に至らない救助の仕方も周知された。
震災を受けて避難所の立ち上げやボランティアの受け入れ、
支援物資の受付と輸送、避難生活の基本の大切さを
教えてくれたのも、この震災だった。
電話の通じない中、非常時に役立つシステムの構築も
あの時に、避難所に設けられた臨時電話の前に
長時間並び続ける被災者がいたからだ。
東海地震の危機が叫び続けられる中で
どこか他人事であった当県以外の地域に
大いに防災意識を喚起した。
私が今、防災30年ののちに思うこと。
「あの震災を忘れない」のではない。
あの震災を経験した人々の、私たちへの思いを受け取ること。
今でも生々しく迫るあの日と共に生きている人たちの思いを
忘れないこと。
彼らに深く感謝する。
https://www.dri.ne.jp/
あの日、そこにいた人々の思いを忘れない。
今を生きるすべての人に。
もう、心も折れて立ち上がる気力も失せる状況。
ボランティアの人がかけてくれた言葉で前を向けたという。
「大丈夫ですよ。私たちが前を歩いています」
阪神淡路大震災での被災経験者のボランティアだった。
読んだとたんに、記している今さえ、涙がこぼれる。
あの地震で被災した人々が、その後の被災地に
一番に駆け付けたことをいくつも聞いているからだ。
あれほどの地震、あれほどの災害、その後の時間が
ようやく進みかけた9年後。
中越地震が発生した時に、真っ先に助けに入る。
1995年の兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)以来、
当時観測史上2回目の最大震度7を記録した地震だった。
鳥取県西部地震でも熊本地震でも東日本大震災でも。
彼らはどこへも駆けつける。
その思いに触れて、押さえようもなく熱いものがこみ上げてくる。
そして、彼らがあの日から、震災に合わないようにと
呼びかけてきてくれていること、進んだ防災減災のための制度に
深く感謝し続ける。
あの日、震災被害にあった地域のラジオが細やかな情報を
流し続け、いかに市民の役に立ったかを評価し、
全国にコミュニティラジオ局が続々と開局された。
今も、コミュニティラジオ局は防災ラジオと称されるゆえんでもあろう。
東海地震に備え、防災情報の収集をし、
また仕事で被災者からの話を聞く機会を多く得、
学んでゆくうちに、いかに阪神淡路大震災がわたしたちに
多くの防災の知恵を授けてくれたか、その事実に胸が苦しくなってくる。
発生の様子。倒壊で命を失わないために。
あるいは、逃げ遅れないために。
今も、たくさんの家屋内外への知恵が教示されている。
あの日。救命措置で一人でも多く救うために、
どれほどの思いで、運び込まれる人々の
処置の順序や、ときに措置の打ち切りをしたか。
あの時。目の前の炎を前に、人々の助けを懇願する様子の前に、
車も入れず、水も出ず、なすすべのない思いを味わったか。
被災者救助に当たった医療関係者や消防隊は、
無念さや無力感から、いつまでも心の傷をおった。
その後、トリアージの制度やD-Matなどが
次々整備され、特殊救助隊や特殊車両の導入となる。
倒壊家屋から助け出された人々の、その後の突然死の関連から
クラッシュ症候群に至らない救助の仕方も周知された。
震災を受けて避難所の立ち上げやボランティアの受け入れ、
支援物資の受付と輸送、避難生活の基本の大切さを
教えてくれたのも、この震災だった。
電話の通じない中、非常時に役立つシステムの構築も
あの時に、避難所に設けられた臨時電話の前に
長時間並び続ける被災者がいたからだ。
東海地震の危機が叫び続けられる中で
どこか他人事であった当県以外の地域に
大いに防災意識を喚起した。
私が今、防災30年ののちに思うこと。
「あの震災を忘れない」のではない。
あの震災を経験した人々の、私たちへの思いを受け取ること。
今でも生々しく迫るあの日と共に生きている人たちの思いを
忘れないこと。
彼らに深く感謝する。
https://www.dri.ne.jp/
あの日、そこにいた人々の思いを忘れない。
今を生きるすべての人に。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
|
|







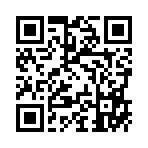

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。