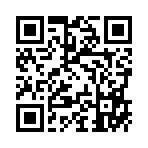2010年06月24日
国民読書年、連続講座01
電子書籍元年だなんていってますねえ。
未来のある日、振り返ったら、そうなのでしょうか。
それでいて、今年は国民読書年でもある。
電子であろうが南だろうが、書籍は書籍、ですか?
◎2010年の国民読書年のキャッチフレーズは、 「じゃあ、読もう。」
関連するページは、こちら。
http://current.ndl.go.jp/node/14976
http://www.gov-online.go.jp/pr/theme/kokumindokusyonen.html
http://www.mojikatsuji.or.jp/2010.html
http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/1188450_1393.html
今私たちが残しているはずのものは、意外と残らないもの。
ちょっと前のレシートを見れば明らかなように、記された文字が消えてゆく。
紙の質の問題もある。
近代史研究の漆畑さんは、明治以降、洋紙が入ったことで、日本の記録が薄らいだといっていた。
それ以前の和紙は、虫食いはするものの、しっかりと残る。
しかも、文字を墨で記していることで、これまた、消え去る心配はない。
燃えてしまいさえしなければ、未来の人々が読むことができる。
今の書籍は、紙にインクを載せてプリントしてあるだけ。
これもまた、時間と共に文字は消え去る。
となると、そこに鉛筆でいたずら書きや書き込みでもしたら、それだけが、残るのだそうだ。
そうなった古文書を見たら、未来人はどのように思うのか、それはちょっと面白いのだが。
静岡の面白い面々が、本を素材に縦横無尽に話しを駆け巡らせる連続講座を設けてくれた。
既に、序章に出かけてみたが、刺激的で、一部アングラっぽくて、何しろ、面白いこと掛け値なし。
いよいよ、正式な第1回目が催される。
~学問所主催 「国民読書年」連続公開講座『書物』~
書籍の未来を考える、活字文化は滅ぶのか
01 禁書と焚書と表現の自由 ―読者の現在
■■■2010年6月29日(火)19時~21時■■■
場所:馬場町会館(浅間通り裏・二瀬川神社内)
会費:1000円(1ドリンク付き)
問い合わせ:090-3455-6807(学問所・鈴木)
かつて図書館に対する市民からの「悪書」廃棄要求と闘った佐久間美紀子さん(静岡市の図書館を良くする会)を講師に招き、現在進行している「非実在青少年規制問題」や、GHQの要請によって戦前書籍が大量に焚書された問題など、読書の自由を押さえ込むさまざまな「禁書」について考えます。
予定されている内容
1 最近の図書館蔵書に対する介入
ちびくろさんぼ(長野)1988
天皇図録(冨山)1990
みどりの刺青(松本)1994
タイ買春読本(静岡)1995
2 青少年条例による有害図書指定
完全自殺マニュアル(岡山)1997
3 検閲と焚書
GHQの検閲とプランゲ文庫
紛失・盗難・廃棄・焚書
カルト宗教の万引き
イラクでの未必の故意
4 収集・利用・保存
地域資料の収集
「マルコポーロ」のバックナンバー
フランス「地獄の部屋」
青空文庫やグーグルのコンテンツ
参考 http://www.geocities.jp/yokusurukais/aicel.html
その後もあるので、今回は無理だという人も、次回以降もお楽しみに!!
未来のある日、振り返ったら、そうなのでしょうか。
それでいて、今年は国民読書年でもある。
電子であろうが南だろうが、書籍は書籍、ですか?
◎2010年の国民読書年のキャッチフレーズは、 「じゃあ、読もう。」
関連するページは、こちら。
http://current.ndl.go.jp/node/14976
http://www.gov-online.go.jp/pr/theme/kokumindokusyonen.html
http://www.mojikatsuji.or.jp/2010.html
http://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2009/1188450_1393.html
今私たちが残しているはずのものは、意外と残らないもの。
ちょっと前のレシートを見れば明らかなように、記された文字が消えてゆく。
紙の質の問題もある。
近代史研究の漆畑さんは、明治以降、洋紙が入ったことで、日本の記録が薄らいだといっていた。
それ以前の和紙は、虫食いはするものの、しっかりと残る。
しかも、文字を墨で記していることで、これまた、消え去る心配はない。
燃えてしまいさえしなければ、未来の人々が読むことができる。
今の書籍は、紙にインクを載せてプリントしてあるだけ。
これもまた、時間と共に文字は消え去る。
となると、そこに鉛筆でいたずら書きや書き込みでもしたら、それだけが、残るのだそうだ。
そうなった古文書を見たら、未来人はどのように思うのか、それはちょっと面白いのだが。
静岡の面白い面々が、本を素材に縦横無尽に話しを駆け巡らせる連続講座を設けてくれた。
既に、序章に出かけてみたが、刺激的で、一部アングラっぽくて、何しろ、面白いこと掛け値なし。
いよいよ、正式な第1回目が催される。
~学問所主催 「国民読書年」連続公開講座『書物』~
書籍の未来を考える、活字文化は滅ぶのか
01 禁書と焚書と表現の自由 ―読者の現在
■■■2010年6月29日(火)19時~21時■■■
場所:馬場町会館(浅間通り裏・二瀬川神社内)
会費:1000円(1ドリンク付き)
問い合わせ:090-3455-6807(学問所・鈴木)
かつて図書館に対する市民からの「悪書」廃棄要求と闘った佐久間美紀子さん(静岡市の図書館を良くする会)を講師に招き、現在進行している「非実在青少年規制問題」や、GHQの要請によって戦前書籍が大量に焚書された問題など、読書の自由を押さえ込むさまざまな「禁書」について考えます。
予定されている内容
1 最近の図書館蔵書に対する介入
ちびくろさんぼ(長野)1988
天皇図録(冨山)1990
みどりの刺青(松本)1994
タイ買春読本(静岡)1995
2 青少年条例による有害図書指定
完全自殺マニュアル(岡山)1997
3 検閲と焚書
GHQの検閲とプランゲ文庫
紛失・盗難・廃棄・焚書
カルト宗教の万引き
イラクでの未必の故意
4 収集・利用・保存
地域資料の収集
「マルコポーロ」のバックナンバー
フランス「地獄の部屋」
青空文庫やグーグルのコンテンツ
参考 http://www.geocities.jp/yokusurukais/aicel.html
その後もあるので、今回は無理だという人も、次回以降もお楽しみに!!
Posted by Hi!ーTJ at 23:54│Comments(0)
│人にぞっこん